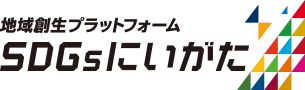新潟県受託事業としてSDGsにいがたが実施する、県内中学・高校を対象にした出前授業の第2回が8月6日、妙高市の県立新井高等学校で開かれました。対象は1年生120人。総務省の国際統計管理官、永田真一(ながた・まさかず)さんが「誰もが生き生きと生きられる社会を目指して」と題して講演し、SDGsのゴールの一つであるジェンダー平等や多様性を尊重することの大切さを伝えました。

講師の永田真一さん
中学・高校での講演は「新潟県SDGs普及啓発事業」の一環で、県内の若者にSDGsをより身近に感じてもらうことが目的です。2025年度は総務省の国際統計管理官室と連携し、「統計から分かる世界や日本のすがた、統計から見えるSDGs」を大きなテーマに10月までに県内4校(中学校2校、高校2校)で出前授業を展開します。新井高校での講演は、7月実施の聖籠中学校に続いて2校目の開催です。
福岡県出身の永田さんは総務省に入省後、奈良県庁での勤務やフランス大学院への留学(ジャーナリズム専攻)などを経験。首相官邸国際広報室では、フランス語担当として安倍晋三元首相の外国訪問に随行し対外広報を担いました。総務省行政管理局では、「オフィス改革伝道師」として新潟市役所の研修講師なども担当。内閣人事局で女性活躍・ダイバーシティ担当として男性育休1ヶ月を推進するなど、「社会の空気を変え、誰もが生き生き働ける組織」への変革を目指して活躍しています。
授業の冒頭で、永田さんはSDGsの基本理念「leave no one behind(誰ひとり取り残さない)」を紹介。事例として、20年ほど前に見かけたという看板の写真を投影しました。「足もとにご注意ください」という日本語の下に、ローマ字で「ASHIMOTO NI GOCHUIKUDASAI」と表記されています。英訳せずに日本語の発音をそのままローマ字に変換していますが、日本語が分からない人には注意喚起の意味が伝わりません。
永田さんは「皆さんはこの看板を見ておかしいな、と思うでしょう。だけど、ここで気付いてほしいことは、自分と考えや背景となる文化、価値観や行動が違う人のこと、一つの事例から全体的なことを想像する力を養うことの大切さ。そして、もう一歩進んで『自分だったらどうするだろう』と考えること。それがSDGsが掲げる、leave no one behind(誰ひとり取り残さない)の精神です」と強調しました。

統計データを交えながらの講演。生徒は真剣な表情で聞き入っていました
永田さんは17のゴールに関連する身近な統計データを使いながら、SDGsを自分事として考え、将来の進路選択に生かすヒントについて話しました。
例えば、「目標1・貧困をなくそう」。全世界では10人に1人が貧困状態にあるという統計データがあります。貧困は「他人事」の問題ではありません。厚生労働省の統計データによると、日本では6人に1人が貧困に苦しんでいます。
永田さんは母子家庭で育ちました。生活を支えるため朝5時に起きて仕事に出掛け、保育園の行事に参加することも難しかった母親の姿を間近に見ていました。その頃に抱いた社会への違和感や疎外感が、公務員を目指す原点になったといいます。
SDGsの17のゴールには、経済、社会、環境の3要素があります。永田さんは「戦後、経済と社会が豊かになると同時に公害が発生してたくさんの人が苦しんだ。では、規制が緩い海外に工場を移せばいいのか? 経済を優先すると、そうした問題が起きる。だからこそ、(SDGsは)国際的にみんなで取り組まなければいけない」と語りました。
「目標5・ジェンダー平等を実現しよう」。家事・育児時間の男女差や警察官の男女比の偏りといった統計データを引用し、政策を決めている人の中に女性がほとんどいない状態では、行政サービスや安全に関わる商品開発にも不都合が生じる可能性があると指摘。「break the chain(連鎖を断ち切る)」の言葉を紹介し、性別に関係なくすべての人が社会参加しやすい環境を整える必要性を強調しました。
講演後の生徒アンケートでは、「普段知ることのできない情報を詳細に知ることができて感動しました」「誰も取り残さないという言葉の重要性を感じました」といった感想が届きました。
(SDGsにいがた事務局)